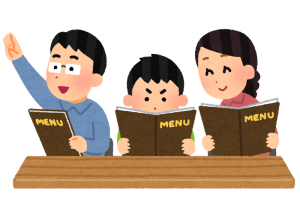
飲食店でメニューを見た時に、「ごちゃごちゃしすぎてて全然決められんよ」という時は無いですか?
気が付いている人は少ないかもしれないですが、「選択をする」というのは、物凄くパワーが必要な行為なんです。
件のメニューの様に、選択肢が多すぎると脳が疲れてしまい、選択する事を放棄してしまうんですね。
選択肢が多すぎると決断できなくなる
影響力の武器 実践編にこんな実験が記載されています。
買い物客が同一メーカーの色々なジャムを試食できるよう、高級スーパーの中に2ヵ所の試食コーナーを設けました。
そのうちの一箇所は6種類の、もう一箇所には24種類のジャムを置きました。
すると、これら二箇所での売上に大きな差が見られました。
どちらの方が売上が良かったと思いますか?
答えは、選択肢の少ない6種類のジャムを置いた方でした。
24種類のジャムを置いたコーナーは3パーセントの人がジャムを購入したのに比べ、6種類の方は30パーセントもの人が購入したそうです。
驚くことに、10倍もの差があったのです。
研究者の見解では、あまりに選択肢が多すぎると、消費者にとってそれぞれを差別化する事が負担となって、決断を下すのが煩わしくなってしまうから というものでした。
この実験結果から、メニューの数、商品バリエーションの数などは、あまり多くしすぎない方が良いでしょう。
実際、プロクター・アンド・ギャンブル社がシャンプーのバリエーションを26種類から15種類に絞った途端に売上が10パーセント伸びたという事例もあります。
決断疲れで衝動買いをする
人は1日に約9,000回の決断を下していると言われています。
決断を繰り返し、決定の質が低下する現象を心理学では「決断疲れ」と呼びます。
決断疲れは不合理な行動を起こします。
例えば、衝動買い。
買い物の際に、値段と販促に関するトレードオフの決断の連続が決断疲れを起し、衝動買いしたいという欲求を抑える意志力が無くなってしまう。
このために衝動買いをしてしまうのです。
つまり、衝動買いを防ぐためには、決断の数を減らす、つまり、買うものを決めていれば良いと云う事になります。
ジョブスやザッカーバーグが同じ服を着ているのも、同じ理屈ですね。
服装の決断を避ける事で、経営判断をに使う決断のエネルギーを保存しているのです。
事実、ザッカーバーグは以下の様に述べています。
「僕は社会への貢献に関係しない決断はできるだけ下さないようにしている。実はこれは多くの心理学的な理論に基づいていることで、何を食べるか、何を着るかなどのたとえ小さな決断でも、繰り返し行っているとエネルギーを消費してしまうんだ。日々の生活の小さな物事にエネルギーを注いでしまうと、僕は自分の仕事をしていないように感じてしまう。最高のサービスを提供して、10億人以上もの人々を繋げることこそ、僕のすべきことなんだ。ちょっとおかしく聞こえるかもしれないけど、それがぼくの理由だよ(vimeo)」
まとめ
メニューや商品バリエーションは多くなりすぎないようにしましょう。
判断疲れにより、選択する事自体が放棄されてしまいます。
逆に、正しい選択をさせたくない場合、言い換えると正常な判断が出来ない状態にするには、連続して選択させ続ければ良いという事になります。
上記の衝動買いの例がそうです。
意図的に決断疲れを起こし、こちらの意図した選択肢を選んでもらう。
交渉等にこのハックを使う事もできると思いますが、余りお勧めは出来ません。
どちらかと云うと、自身が騙されない為に、この知識を覚えておくのが良いでしょう。


